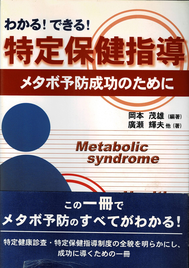介護の進化を目指し、AIやロボット開発などを行ってきた岡本茂雄氏。39年間一貫してこの分野に携わり、現在も産業技術総合研究所や東京大学高齢社会総合研究機構の研究者、株式会社ノバケアのCEOとして最先端分野の第一線に立っている。
AIというと、人間と能力を競い合ったり、人間の仕事を代替するイメージが浮かびます。介護のAIとはどういったものなのでしょうか?
当面はAIが人間を追い越すことはないでしょう。私の立ち位置は、ケアそのものを進化させる道具として、AIやロボット使いこなすことです。以前と比べて、「人間は高度な観察力をもってやるべきところをやり、AIにできるところはAIに任せる」という考えが通じるようになっています。
もちろん、AIはさまざまな分野での活用が進んでおり、一括りにはできません。まずは「アルファGo」と対比するとわかりやすいでしょう。アルファーGoとは、米グーグル傘下のディープマインド社が開発した囲碁のAIです。2015年にプロの囲碁棋士を破った初のコンピュータ囲碁プログラムとなり、日本でのAIブームの火付け役となりました。
介護のAIとどう違うのか?囲碁では「勝つことが正しい」のであり、開発者はAIにそのような定義を与えればよかったわけです。初代アルファGoには、今迄の対戦パターンを学習用データに利用しました。その強さは人間の知見の延長に過ぎなかった。ところが2017年に同社が発表した「アルファGoゼロ」では、AIによる独自学習が実装されました。教えるのは囲碁のルールだけで、その後は自分自身やAI同士の対局で独自の成長を遂げ、最強の打ち方を編み出していったのです。開発開始のたった40日後には、初代アルファGoに対して100戦全勝を果たし、天才と言われた世界のトップ棋士、柯潔氏にも3局全勝を挙げました。このように囲碁のAIは大きく進化しましたが、一貫しているのは「勝つためには正解がある」ことです。
一方の介護分野はどうでしょうか?根本的に違うのは「必ずしも正解がない、あるいは複数の正解が存在する」と言うことです。要介護状態の人にとって、走れるようになることがベストなのでしょうか?そうではありません。もちろん、寝たきり状態は誰も望みません。では、どのような状態になることを望むのか?私は、幅広い意味での自立だと思います。
最終的に家族の負担軽減と当事者の自立やADL(日常生活動作)の改善のどちらに重点を置くのかについては、各家族における価値観の問題です。ところが、日本の介護の実態を見ると、かなりの部分で家族の介護負担軽減を重視している。そこで私は自立やADLの改善を重視するケアプランを選び出すことから始め、それらを「教師データ」としてAIに徹底的に学ばせていったのです。
そうしたAIの開発で重要なのは何でしょうか?
擬人的ですが、教育方針とでも言うものです。「どのような目的でどのようなデータを与えるのか」は人間の役割です。放っておいて、AIが勝手に賢くなることはありません。むしろ与えられたデータによって、そこにあるものを学んでいくのです。だからこそ、学ばせるデータが重要なのです。ここがコンピュータープログラムとの本質的な違いです。コンピューターはプログラム通りにしか計算できませんが、AIはデータに基づき自分でプログラムを改変できる。ただし、どの方向に改変するかは人間が教えなければなりません。
ちなみに、教えるとは、どのようなデータを教師として学ばせるかと言うことです。ここが難しい。環境汚染を止めるのであれば、人類を滅亡させた方がよいとの結論を出すかもしれないからです。「高齢者の自立やADLを大切にするのか」或いは「家族の負担軽減を大切にするのか」では、教育方針やデータの与え方によって全く異なる答えを導きだすことになります。優れたAIを育てるためには、医療・介護分野の高い見識はもちろんのこと、開発者の人間性や哲学までが求められると言ってもよいでしょう。
AIにより当たり前になるのが「科学的介護」です。一般的に今までの介護現場は職人芸の体質が根強い。再現性のある研究とデータに基づいて「この人にはこういう介護」とするのではなく、介護の上手な人のやり方を学ぶやり方です。現場毎に介護方針や方法が異なり、データとしても蓄積されてこなかった。介護のマニュアルも然りです。例えば体位変換では「足を広げて患者の重心を前に倒す」とありますが、それが何センチなのかは書かれていません。剣術の極意書のようです。「百人百様の介護」と現場の人は言いますが、そもそも高齢者の状態を評価する方法がバラバラで、見る人によって違うのが現実です。
これが芸術の世界であれば、データは必要ありません。ミロのビーナスやモナ・リザをデータの蓄積で超えることはできないからです。しかし、学問の世界は違います。医学においてヒポクラテス時代のやり方を踏襲している医師など皆無です。
AIは数値化された巨大なデータを処理し、「こうしたらよくなる」「こうしたら悪くなる」というパターンを瞬時にはじき出してくれます。一方でその手前のアセスメント段階での課題が大きく三つある。一つ目は、容態像の把握において職種毎に異なる評価手法がとられていることです。ケアマネジャーはMDSやICF、看護師はNANDAやNIC、介護福祉士は包括的自立支援プログラムや日本介護福祉士会方式、リハビリテーション技師はFIMやBIなど多岐に渡り、データベースとしての共有は困難な状況にあります。(※)
二つ目は、介入内容や量の把握においても、現場毎に異なり共通の用語がないことです。例えば「排泄介助」と言ったときに示す内容はさまざまで、業務プランや業務記録の共有ができにくい状況にあります。結果、AIやロボット導入による改善や業務開発、全体としての生産性向上も困難を極めることになっています。
三つ目は価値観・ゴールの多様性です。生活においては多様な価値観があり、家族の意向なども関わってきます。正解が複数存在し、何を選ぶかは本人や家族の価値観により異なります。
とはいえ、たとえば評価手法を統一する必要はありません。画一的なアセスメントは、介護の質の低下を招くためです。IT化が進んだ現在、アセスメント手法は多様であって然るべきです。医学的に判断するところとリハビリ、理学療法士や介護福祉士が判断するポイントは異なるのであり、違う言語、違う方法でアセスメントするのは当然です。画一化を目指すのではなく、対象者をADL別にし、介護者の動作をできる限り細かく分け、介護者の経験年数別(スキル別)に特徴を分析するべきです。
介入内容については、介護業務分類の標準化が進んでいます。また、容態像の把握については、コンバーター(変換プログラム)で容態度を医師や看護師、介護福祉士、ヘルパーにわかるように読み替えることが可能になりつつあります。これらの大量で多様なデータを、処理するのにもAI技術は役立ちます。
ご自身が介護に携わるようになった経緯をお聞かせください。
1983年に東京大学を卒業後、民間の立場で医療・介護に貢献しようと思い、化学製品の製造・販売を行う株式会社クラレに就職しました。当初は抗がん剤や人工臓器の開発を担当したのですが、ある時上司から「これからは在宅医療や介護分野が大きく伸びる」との理由で調査を指示されました。しかし、当時の日本には在宅医療に携わる人はほとんどいません。少ない手がかりを頼りに調べたところ、東京都神経科学総合研究所(現在の東京都医学総合研究所)が、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者を自宅診療していることを知りました。すぐ電話をかけ「在宅医療について知りたい」と話すと「担当者に同行して体験したらどうか」とのこと。百聞は一見に如かず。絶好の機会と思い現場を訪問したのですが、そこでの光景に衝撃を受けました。いわゆる疾病を治すための治療が行われてはおらず、そこで看護師が行っていたのは、幅広く患者の生活を支える行為でした。今でいう「介護」そのものです。
「この分野はこれから絶対に重要だ」と直感し、人生をかけようと決めました。早速会社に介護ショップの開設と運営を提案し、自らが担当しました。当時は「介護」という言葉が一般的ではなかったので、わかりやすく「車椅子からオムツまで」をキャッチフレーズにしました。その後は株式会社三菱総合研究所、明治生命保険相互会社、訪問介護サービス大手のセントケア・ホールティング株式会社でさまざまな介護ビジネスを手掛けながら科学的介護の研究に没頭することになります。今振り返ると、よく会社が認めてくれたものです。(笑い)
自立支援のAIを目指した経緯についてもお聞かせください。
二つの経緯があります。訪問介護の現場で、高齢者の自立への思いを知ったことが一つ目です。部下とある現場を訪れた時のこと。おばあちゃんが「孫の結婚式がもうすぐあるけど、私のようなものが出席すると迷惑をかけるから」と言うのです。私は「車椅子でもよいから出席できるように努力をしてもよいのでは」と自立支援介護を持ちかけました。すると、二か月後には式に参列できるほどになったのです。その時の「ありがとう」は、夜間のおむつ交換での「ありがとう」とまったく違う響きでした。当事者にとって自立支援が絶対に必要と実感した瞬間です。
当時、2000年に介護保険が施行され、ケアプランという概念が生まれました。介護保険制度の創設が画期的だった理由は三つあります。保険でありながら、予防も手当てしたこと。霞が関ではなく自治体側が事業規模を決める仕組みになったこと。そしてケアプランです。私はケアマネジメントこそが、介護保険における最大の発明だと思っています。
課題は「どのようなケアプランを行うべきか」でした。私は「よいケアプランとは何か?」に対する答えを見出さないかぎり、ケアプランを作成することは困難と考え、旧厚生省の関係者に議論を持ちかけます。そこから同省の協力を得て、被介護者への声かけに関するケース・コントロール研究(症例対照研究)を実施しました。この研究では、さまざまな驚きがありました。例えば、行動を促す誘導の声かけを増やすと問題行動が起こりやすくなった一方で、雑談を含むコミュニケーションを増やすと、結果的にADLが改善されたことがあります。
現在もそうですが、ケアプランは主にケアマネジャーが要介護者のADL、健康状態や要望、介護を担う家族の生活状況などを調べて作成しています。大きな課題は、「家族の介助負担を少しでも軽減する」ことに主眼を置いたものになりがちなことです。しかし、必要以上の介護は、要介護者の行動量を減らし、筋力・気力を衰えさせる結果につながりかねません。これでは本末転倒です。本来、ケアプランは要介護者が日常生活で自立できることを目指すべきです。過剰な介助を控え残存能力を使うことが、筋力や運動機能の回復につながるのです。認知症については、BPSD(認知症の行動・心理症状)が現れることが問題を引き起こします。AIによって具体的にBPSDの発症予測(たとえば1時間後に徘徊が始まるなど)ができれば、それを防ぐためのケアを効果的に施すことができると考えています。
高齢者が要介護者になる2大原因は認知症・脳卒中と高齢による衰弱ですが、どちらも適切なプログラムを組めば、回復も不可能ではありません。結果がついてくると、当事者はもちろんのこと、家族や介護にかかわる専門家の意識が変わります。「とにかく家族の負担を軽減すべきだ」という思いから、「リハビリで頑張れば社会参加できるかもしれない」、「家族と幸せな生活を営める」というように。
もちろん、介護において「現状の課題分析」は極めて重要です。しかし、現状の問題を解決するための機能補填に終始してしまうと、結果、「自立」に向けたケアは困難になります。例えば、トイレまで歩いて20分かかる方に対して、「援助」という方法で車いすなどで機能補填をすると、自立を目指すことが難しくなる。家族の介護負担の軽減だけを目的としてしまう場合のデイサービスの利用も同様です。結局、家族の要望に従う「御用聞きプラン」になりがちになり、その結果、要介護者の自立を難しくしてしまいます。在宅ケアで生活できるのに、デイサービスにあずけられてしまう。女性は他の高齢者としゃべるからまだいいのですが、男性の場合、新聞を読んで「ぼーっ」としている方を見かけることもありました。
こうした現状を打開できると考えたのが、AIによるケアプランでした。AIを活用することで、自立促進による要介護度の改善や、過剰介護の減少による自立促進を目指したのです。
自立支援のAIを目指した二つ目の経緯についてはいかがでしょうか?
2015年に研究仲間とアメリカのシリコンバレーに医療・介護の視察に行ったことです。当時私は、セントケア・ホールディング社で介護ロボット、AI、認知症ケアの分野で新規事業開発を担当していました。視察の目的は、医療保険制度改革であるオバマケアの成否を有識者と議論することと、AIがヘルスケア市場においてどのように活用されているのかを調べることです。
AIベンチャーの会社訪問で驚いたのは、会議の参加者の3割が現場の医師であったことです。日本の大企業だと、まず全員がエンジニアです。「AIの起業家にこれだけの現場の医師がいる。介護のAIの開発にも現場の医師が参加している。」目からウロコが落ちた思いでした。
共同開発の可能性を見出した私たちは、二か月後に予算を組んで再びシリコンバレーを訪問しました。ところが当方の予算とシリコンバレーで必要な額では桁が違っていた。「介護分野でAIを用いるのは面白いが、予算が低すぎる」と言われたのです。諦めかけていたところ、最後の訪問先だったスタンフォード大学のAIセンターで予想外の展開が待っていました。

「日本は公的介護保険制度が充実しており、介護サービスの提供や機器のレンタルに対して、要介護者の身体状態に応じて7段階で上限金額の異なる保険給付が社会保険から支給される」「国はこの要介護度認定のために、『自分で食事ができるか』『自分で歩けるか』など74項目に及ぶ詳細な身体状態の検査を行っている」「この膨大なデータを、AIを使ってより良い介護プランの作成に活用できないか?」と提案したところ、若きAI研究者のグイド・プジオル博士が目を見開いたのです。「そんな介護システムはアメリカにはないし、聞いたこともない」と。続けて「『日本の要介護者約600万人×74項目×2000年の制度開始から15年分』は凄いビッグデータだ!イノベーションが起こせる!」と興奮冷めやらない様子です。「非常に面白いし人類のためになる。予算は持ってきているだけでいいから一緒に取り組もう」と言ってくれたのです。
プジオル博士のおかげで、一気に共同開発の話が進みました。同大学が優れているのは、AIと医学の両方の分野から、それぞれ研究者が揃っていたことです。しかもスピードが速かった。テーマは「ケアプランでどういうサービスをどれだけ利用すれば、どれだけ高齢者のADLが改善されるか」でした。2年間の共同研究では、たくさんの発見がありました。例えば同じADLの方でも、進行性疾患と慢性期疾患では、AIが異なる自立支援プランを弾き出してきたことがあります。AIはその時点の状態だけでなく、将来の変化をも鑑みた自立支援プランを作成するのです。
国内外での経験と実績がAIの企業設立につながったのですね。
政府は、2016年にビッグデータやAIを活用し、「予防・健康管理」と「自立支援」に軸足を置いた新しい医療・介護システムを2020年までに本格稼働させる方針を明らかにしました。手応えを感じた私は、介護のAIを日本の制度に取り入れてもらう計画を立案。さらにプジオル博士からの「スピードを速めるため、介護AIの会社をつくってください」という要望もあり、政府系ファンドの産業革新機構を筆頭に、セントケア・ホールディング、エンジニアリング会社の日揮、デイサービス大手のツクイ、社会福祉法人こうほうえんなどから総額15億円を調達し、自立促進・重度化予防のケアプランを提供する株式会社シーディーアイを設立したのです。同時期にプジオル博士は米国でActivity Recognition社を設立し、日本の介護保険データとアメリカのAIを合体させる事業を開始しました。
シーディーアイ社ではケアプランのAI「MAIA」を開発しました。要介護度認定の際の74項目の調査結果をインプットすると、AIが要介護者の「自立支援」を目的としたケアプランの原案を一瞬で策定する仕組です。たとえば、膝が変形して歩けない73歳の要介護2の女性について、「デイサービスの利用を週3回から週1回に減らす一方、新たに訪問リハビリを月に8回、訪問入浴を適宜利用する」というケアプランが提示されます。その原案をもとにケアマネジャーが、本人の希望などさまざまな要素を加味して最適なプランに仕上げることになります。要介護者のADLを改善し、自立生活を実現することを目的に要介護者の自立支援プランを作成する世界初のAIでした。
早速いくつかの自治体と協定を結び実証研究を重ねたところ、新たな発見がありました。例えばAIが「ショートステイの月1回利用」というプランを提示したことがあります。通常は、そのようなショートステイの使い方はあり得ません。ところがそれに沿ってケアプランを実行したところ、要介護者は月1回のショートステイに備えて早起きするなど生活リズムを整える、社会参加の機会のために化粧を始めるなど、自立志向が高まる効果が見出されたのです。結果として、対象の方のADLは大きく改善されました。このようなAIによる気付きは、ケアプランの進化への大きな実りになりました。
現在はノバケア社のCEOとして陣頭指揮を執られています。
当社は少数精鋭で、日本のAIや介護ロボットの第一人者4名で設立しました。目的はビジネスというよりも、AIを持続可能で自立した生活を営める高齢社会の創生に役立てることです。そのために、これまでもノウハウを広く普及するために、「介護ショップ経営マニュアル」、「訪問看護アセスメント・プロトコル」、「疾病予防支援サービス」など、多くの本を執筆してきました。開発の無駄を排し、大組織では2時間かかるような会議を5分で終わらせています。皆、やりたいことが山のようにあり、その実現の芽が出始めています。さすがに自分たちだけではできないのと、後任を育てねばならないと考え、若手社員を4人増やしたところです。
現在開発しているのは、機能訓練によるADL改善を予測し、最適リハビリプランを策定するAIです。要介護者であっても、生活期のリハビリに取り組めばADLを改善できます。MCI(正常な状態と認知症の中間であり、記憶力や注意力などの認知機能に低下がみられるものの、日常生活に支障をきたすほどではない状態)になっても、もとに戻すことが可能です。そのためには何をどうすればよいのか、例えば自転車や歩くことがよいのか、最適解を出し、そのプログラムを継続すると1年後にどのような状態になるのかを予測するAIです。
共同研究も行っており、東京大学高齢社会総合研究機構(飯島教授)とは、AIによる健康まちづくりに取り組んでいます。テーマは地域特性に応じた適切なフレイル予防策の提案です。例えば秋田県や青森県は要支援者が少なく、要介護者の割合が多い。寒冷な気候や塩分の摂取量等の理由による脳卒中で一気に悪化しやすいのではないかと予測されます。一方、静岡県は要支援者はある程度多いのですが、要介護者の割合が少ない。こちらは気候に恵まれているため、外出する機会が多いからではないかと予測されます。ただし、まだ結論には至っていません。このため、継続する研究として、AIに地域特性(住民意識、食性、社会資源など)を学ばせることで、外出したくなる公園や緑地を作るとか、塩分を抑える教室指導を増やすといったフレイルや要介護者の発生を抑える政策を立案することを目指しています。
64歳になられたとのことですが、まだまだこれからですね。
自分では、多くの20代より頭が柔らかいと思っています。AIに関する知見やアイデアでは、大企業のエンジニアには負けないつもりです。今も、そのために勉強をし、また日々の課題発見の姿勢を続けています。これからも「自立に向けた介護」が当たり前になる社会に向け、発明や開発の努力は怠りません。高齢化が進み、余命が延伸するなかで、健康な時間、自立した生活を過ごせる時間をいかに長くするかは、私たちにとって非常に重要なテーマなのです。「自立に向けた介護」を確立することができれば、日本は、これまで蓄積した介護に関する膨大なデータと高齢者医療の知見をもって、介護のあり方を世界に発信できるでしょう。そうすることで、日本から世界に「介護のあり方」を発信できると信じています。
岡本茂雄(おかもと しげお)氏
株式会社ノバケアCEO
国立研究開発法人産業技術総合研究所招聘研究員
1983年 東京大学医学部保健学科卒業
株式会社クラレ(1983年)、株式会社三菱総合研究所(1990年)、明治生命保険相互会社(1997年)、セントケア・ホールティング株式会社医療企画
本部長(2013年)、株式会社シーディーアイ代表
取締役社長(2017年)を経て現職。
介護制度、認知症、生活習慣病、保険数理、社会保険などに複合的な知見を有し、新規事業領域について複数の事業会社設立を行う。厚生労働省、経済産業省等の官公庁、東京大学高齢社会総合研究機構、東北大学医学部などの学識者、AI・IoT技術者、社会福祉法人、医療法人など幅広いネットワークを持つ。